Web公開日: 2010年10月19日(火曜) / 大幅加筆・編集: 2023年 5月27日(土曜)
F1GPでは、車体底面で発生させる空力ダウンフォースを減少させる事を目的に、
1995年シーズンから、ステップ ド・フロアの車輌規則を導入した。(下図)
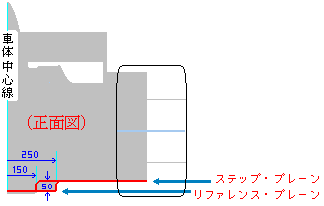
この規定内容は、
リファレンス・プレーンの幅は、車体中心線より外側へ 150mm以上、250mm以下でなければならない。
ステップ・プレーンの幅は、車体中心線より外側へ 150mm以上、700mm以下でなければならない。
text & illustration by tw
Web公開日: 2010年10月19日(火曜) / 大幅加筆・編集: 2023年 5月27日(土曜)
F1GPでは、車体底面で発生させる空力ダウンフォースを減少させる事を目的に、
1995年シーズンから、ステップ ド・フロアの車輌規則を導入した。(下図)
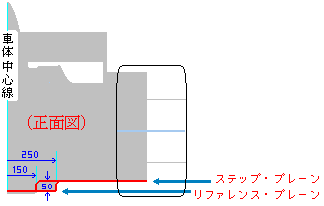
この規定内容は、
リファレンス・プレーンの幅は、車体中心線より外側へ 150mm以上、250mm以下でなければならない。
ステップ・プレーンの幅は、車体中心線より外側へ 150mm以上、700mm以下でなければならない。
そして、リファレンス・プレーンより50mm上方にステップ・プレーンがなければならないと規定された。
この規定により、前(1994)年度のF1マシンよりも、サイドポッド底面と路面との隙間が 50mm も大きくなり、
グランド エフェクト(=地上効果。車体底面と路面とが吸着する力、つまりダウンフォース)が低減された。
このステップドボトム・レギュレーション下での、空力デザインでポイントとなるのは、
「リファレンス・プレーンとステップ・プレーンの段差の側面の幅」を、
300mm〜500mm の範囲であれば、空力デザイナーが自由にデザインできた事なのだ。


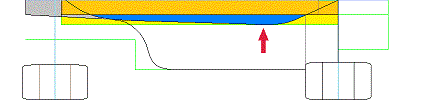
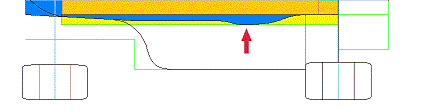
ステップ幅の設定は、車体の『前後ダウンフォース発生 中心位置』の辺りで最も幅が広くなる形状としていた様だが、
サイドポッドの「下面全域の流速」はライバル勢に比べて低かった様で、L/D(ダウンフォース発生量あたりの空気抵抗)は効率が悪く、車体のドラッグ(=空気抵抗)は大きかった様だ。
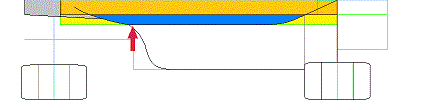
この書き換えられたレギュレーション文章の隙を突いたのが、ブラウンGP、トヨタ、ウイリアムズで、彼等はマルチ ディフューザーを実戦投入した。
それは、ステップ側面の後部にエア インテークを設け、そこから立体的なディフューザーの上下の空間を使って、少しでも多くの車体底面の空気を引き抜くアイディアだ。
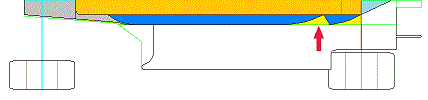
これは非常に大きなアドバンテージがあり、結局レギュで合法とされ、各チームがこぞって追従する事態となった。
この(2009)年、ブラウンGPはドライバーズとコンストラクターズの両タイトルを獲得している。
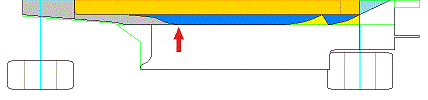
参考になる情報源として、昔の某F1チームの空力エンジニア氏の話によれば、
「サイドポッド上面にあんぱん1個乗せても それほど大きな影響は無いが、車体底面に髪の毛1本テープで貼り付けたら空力性能は壊滅的になる」という事であった。
(このページの最終更新日: 2023. 5.27土)
[Site TOP] [BOX]